
仕事でも私生活でも効率を追い求め、気づけば心の余白を失っていませんか。そんなせわしない日々を送る人たちに届けたい「MCKK(エムシーケーケー)」は、”寄り道の感性を育む”をコンセプトとした香りのブランド。感性を研ぎ澄まし、心に余白をもたらすような商品を提案しています。ファウンダーの閏間(うるま)さんに、ブランドに込めた想いなどを伺いました。
ブランド誕生のきっかけとなった”嗅覚を研ぎ澄ます”体験

――「MCKK」はどのようなブランドですか?
閏間 「寄り道の感性を育む」というコンセプトのもと展開している香りのブランドです。私はMCKKを立ち上げる前、IT業界に身を置いていたのですが、タイパ・コスパばかりを追う日々を送るなかで、精神的な豊かさが失われていくことに疑問を感じていました。
疑問を抱きながらも目の前の仕事をこなしてきましたが、転機はコロナ禍。キャンプに行く機会ができ、自然に触れたときです。土や木、焚火の香りを嗅いだところ心が整うような感覚に包まれたと同時に、”普段いかに嗅覚を使っていないか”ということに気がつきました。
情報化社会のなかで視覚と聴覚はたくさん使う機会がありますが、嗅覚が必要になる場面はなかなかありません。だからこそ、香りを通じて”感性をひらく(=研ぎ澄ます)”ことで精神的な豊かさを取り戻せるようなブランドを立ち上げました。
【参考】MCKKブランドストーリー
日本特有の文化や美意識が息づく商品

――MCKKで展開している商品のこだわりを教えてください。
閏間 MCKKでは現在、ハンドソープとお香を取り扱っています。”手を洗う”という行為に着目したMCKKのハンドソープは、神社にある「手水舎」がきっかけで生まれました。神社の参拝前に行く手水舎には、衛生面だけでなく心身を清める意味があります。その感覚を日常に取り入れたくて、ヒノキの香りと繊細なスクラブを配合したハンドソープをつくりました。
スクラブとして使う素材は、さまざまなものを試した結果、桃の種に辿り着きました。桃は昔から日本で神聖な果物とされていますし、肌当たりも私が求める繊細さをもった理想の素材でした。さらに天然由来成分の比率を高めるなど、こだわりを追求していった結果、開発には1年以上かかってしまいましたね。
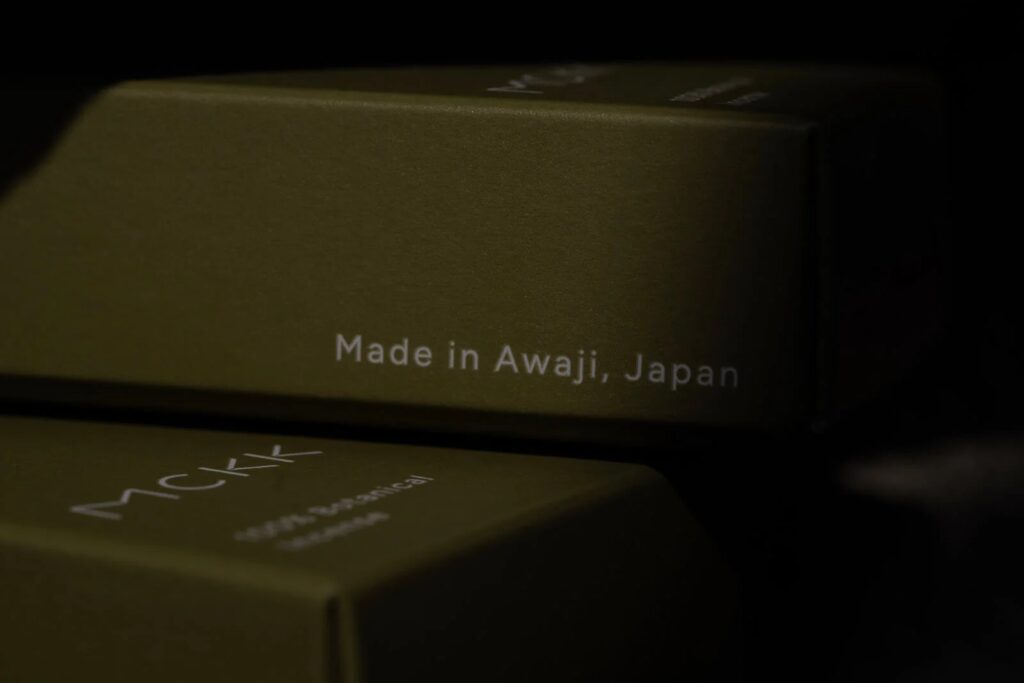
――閏間さんのこだわりが詰まった素敵な商品ですね。では、お香は?
閏間 お香は、日本の香道文化にインスピレーションを得てつくりました。香りを「嗅ぐ」ではなく「聞く」と表現し、自分の内面と向き合うツールの役割を持つ。世界的にもめずらしい、日本独自の美意識が特徴です。
MCKKのお香は、日本でのお香文化の発祥の地である淡路島で製造しています。木の粉末に精油を練り合わせる伝統製法で、100%植物性。熱によって香りが変わるため、精油と粉末のブレンド比率の調整には特に時間をかけました。
香りの名前を「安息」「活力」「集中」という抽象的な言葉にしたのは、香りの感じ方は人それぞれだから。その日の気分で、自分なりの解釈を楽しんでほしいとの思いで名付けました。お香には植物性100%の精油を使っているので、香りが過度に残ることなく、煙とともに香りの余韻も優しく消えていきます。この儚さこそが、感性を豊かにすると考えているんです。
慌ただしい日々に、精神的な寄り道をする時間の豊かさを

――MCKKの商品を世に生み出してよかった、と感じる瞬間はどんなときですか?
閏間 やはり、お客さまから嬉しい言葉をいただいたときですね。私が直接うかがったのは「気分転換になるから積極的に手を洗いたくなる」(ハンドソープ)とか、「嗅覚が浄化されて疲れがリセットされる」(お香)というお言葉です。特にお香を愛用している方は、排気ガスや強すぎる香水など、日常で刺激の強い匂いに囲まれて過ごしたあと、家に帰ってお香を焚くと柔らかい香りに気持ちがリセットされるそうで。MCKKが、思考をリセットして心を整えるスイッチになれている、と思うとすごく嬉しいです。
目の前のタスクに追われていたり、「〜しなければならない」という思考に囚われていたりすると、どうしてもじっくりと心を整えるような時間が取りづらくなってしまいます。そんなときに、火をつける・消す、手を洗うという体験や香りを通じて、精神的な寄り道をする時間の豊かさを感じてもらえたらと思います。
――効率を追い求める日々に、香りという寄り道を。MCKKが提案するのは”感性をひらく”という時間です。手を洗う、香りを嗅ぐ。何気ない瞬間が、心に豊かさや余白を生み出してくれます。
【リンク】
・MCKK公式サイト
【購入はコチラから】商品一覧








